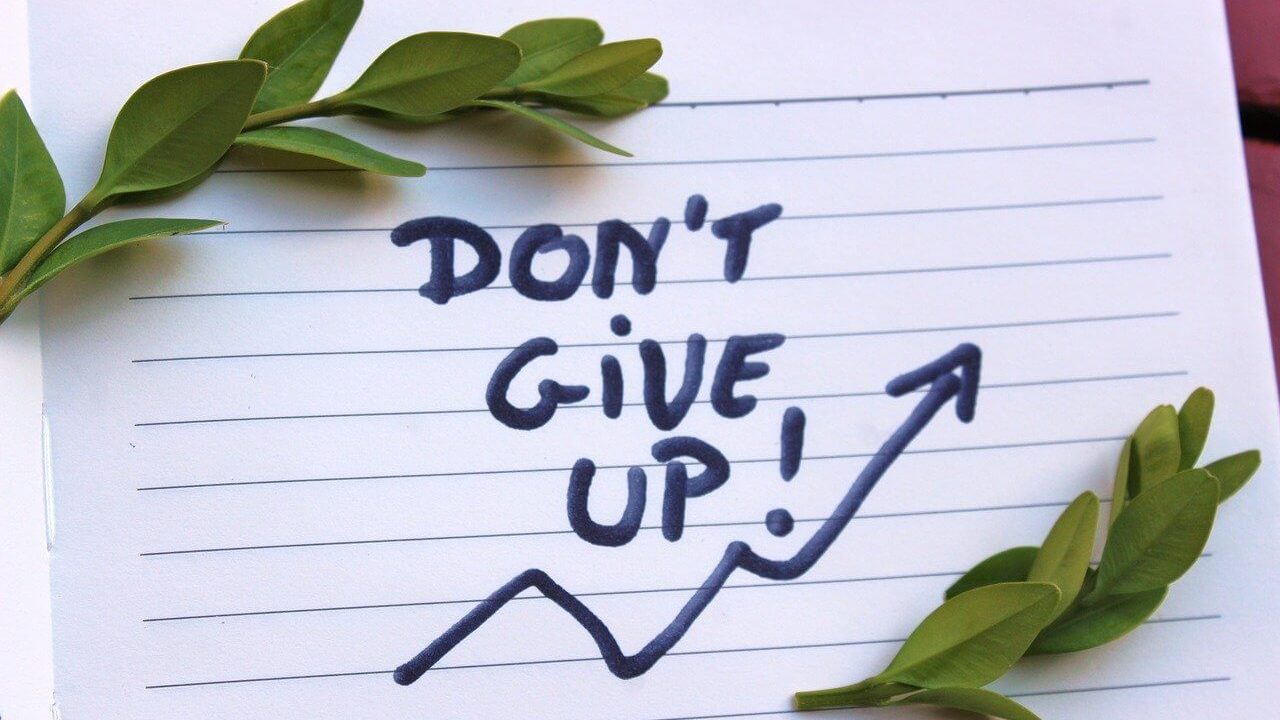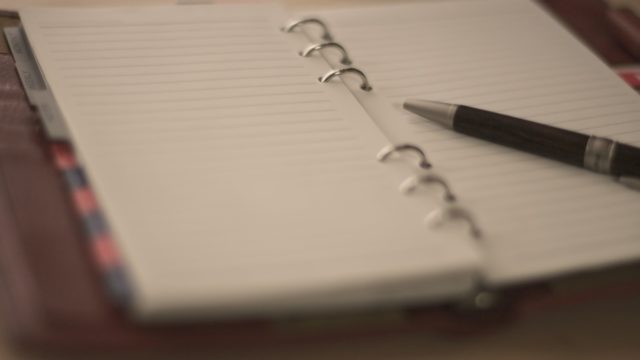通訳案内士の合格率や難易度が、気になっている人いますか?
わたしも受験を決めた時は、合格点や過去のデータを調べたりしました。
この記事を書いているわたしは、全国通訳案内士です。
通訳案内士の難易度について、ずっと思っていたことがあります。
全国通訳案内士の合格率とか難易度とか言うけれど

全国通訳案内士の合格率や難易度って何なのでしょう。
わたしが思うにそれは「自分との戦い」です。難易度など下記に詳しく説明していきます。
全国通訳案内士の合格率と難易度
全国通訳案内士の合格率は過去のデータを見ると、年ごとに変動しているように見えます。
日本政府観光局(JNTO)の「通訳案内士試験ガイドライン」によって合格基準点が定められており、その基準に達した受験者が合格とされるからです。
過去10年の記録では、全ての受験者の合格率は平均で8.5%から25.5%の間を推移してきました。(各年度で数値は順不同)
2010年度以後の合格率については...
- 最も高かったのが、2013年度(平成25年度)の25.5%
- 最も低かったのは、2019年度(平成31年/令和元年)の8.5%
です。(英語を始めとする全ての言語の平均値)
なお、全国通訳案内士試験で2019年度の合格率は全ての言語で一桁台に突入しており、数字データを見る限り「試験内容の難易度が上がっているのでは?」と受け止められます。
タイ語に至っては、2019年度の合格率ゼロ%でした。受験者からすると絶望的な気持ちになるかもしれません。
ですが、合格率=試験の難易度と見るのは少し単純に過ぎる気がします。
全ての受験者の語学力や教育背景は異なり、合格率が比較的に高かった年度でさえ不合格の受験者は確かに存在するからです
タイ語の通訳案内士ゼロ%に関しては、そもそも受験志願者数が少なかったために起こり得た事象であるとの解釈もできます。
合格率はあくまでも受験者全体の平均であり、あなたが合格する確率とは必ずしも重なるとは限りません。
すなわち、通訳案内士の合格率が低いからと言って、それを理由に成功を諦めるのは無意味ということです。
通訳案内士の国家試験の合格基準点
全国通訳案内士の国家試験の合格基準点は、前章に述べた通り日本政府観光局(JNTO)の「通訳案内士試験ガイドライン」によって定められています。
全国通訳案内士(国家資格)の合格ラインは下記の基準です。
- 外国語
原則70点が合格基準点(各科目100点満点)
- 日本地理
- 日本歴史
原則70点が合格基準点(各科目100点満点)
- 一般常識
- 通訳案内士の実務
原則30点が合格基準点(各科目50点満点)
- 口述試験
各項目の評価基準に照らして7割に達しているか
受験者の得点分布が基準と大きく乖離している場合は、事後調整もあるそうです。
これとは別に、検定試験による科目ごとの免除制度もあります。
通訳案内士で言語別の合格者数
全国通訳案内士の言語別の合格者数ですが、年度ごとに推移してきました。
考えられる理由として
・受験者数に年度ごとの増減が見られること
・試験の出題傾向に若干の変化が見られること
などが挙げられます。
受験者数や合格者数の変化の主な要因は、社会情勢による影響だと考えます。
例えば「第二次韓流ブーム」が巻き起こった2010年度と2011年度の韓国語受験者数は、目に見えて増えていますが、母数が増えたことに比例して合格者数も増えました。
しかしながら、政治情勢で国際関係が冷え込んだ昨今、韓国語による通訳案内士の受験者数もやはり減っているところです。
似たような変化は、英語など他の外国語受験者数にも見受けられます。
わたしの仮説ですが、一例として(英語受験の場合)
・オリンピックの開催地が東京に決定した2013年→翌年の受験者数が増えた
→それにより合格者も増えた(その分、合格率は低下?)
・ラグビーワールドカップ2019大会の開催地が日本に決定した2015年→翌年の受験者が増えた→それにより合格者も増えた(その分、合格率は低下?)
等、何等かが引き金となって、通訳案内士の受験者数は増減していると考えられます。
そして、ここでも注目したいのが、「合格率の変化の主な要因は、おそらく合格ラインの変化によるものではない」ということです。
というのも、全国通訳案内士試験の採点は「相対評価」ではなく「絶対評価」だからです。
全国通訳案内士の難易度および合格率の受け止め方

ここからは、全国通訳案内士試験に受かる基準点や難易度に対する考え方です。
点数による通訳案内士の難易度について
全国通訳案内士の難易度ですが、相対評価ではなく絶対評価で合格ラインが決まっています。
相対評価と絶対評価の違いは下記の通りです。
- 相対評価…受験者のうち、定められた上位何%に相当する人が合格者とされる
- 絶対評価…受験者のうち、定められた合格基準点をクリアした人が合格者とされる
言い換えると...
合格率8.5%の年度であれば、全受験者の内の上位8.5%が合格者という意味ではなく、基準点をクリアできた受験者の割合が結果的に8.5%だったということです。
つまり受験者が注視すべきは、他の受験者の実力ではなく「自分自身が合格基準点をクリアできるか否か?」であり、ライバルは他者競合ではなく自分ということになります
ということで、全国通訳案内士の合格率や難易度とは「自分との戦い」なのです。
年度で変わる通訳案内士の合格率について
前章までに見た通り、全国通訳案内士の合格率は年度ごとに変動しています。
数値が変化してきた要因として様々な社会事象が絡みあっており、その時々で難易度的に有利な受験年度があるのでは?と憶測してしまうのは無理がないことです
記憶に新しいところでは、TOEICによる英語科目免除のガイドライン変更がありましたね。
とは言え、通訳案内士に受かった人は全て努力と行動をした人達です。何も行動をしなければ幸運はどこにも訪れようがありません。
わたしの仮説ではありますが...通訳案内士の難易度に関わる要因一例として
・社会情勢
・国際関係
・国際イベント
・オリンピック
・ワールドカップ
・クルーズ船の急増
といった外的要因があり、受験者心理にも何等かの影響は出たものと思われます。
実際、わたしが受験を決意したのは、「何だか最近やけに外国の船が港に入るようになったな」と感じ始めた頃で、それに伴い通訳案内士という資格に注目が集まり始めた時でした。
近い将来にインバウンド界隈で何かが起こるかも、という気運が高まるにつれ外国語需要への期待も高まり、通訳案内士に多少なりとも将来性を感じたので参入を決めました。
対する2020年度の今春は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、移動は制限されインバウンド需要自体が無くなっています
それにより、通訳案内士の受験者の気分にも何かしらの変化は表れているはずです。
今のところ、8月の国家試験は行われる予定ですが、例年と違う兆候が出てくるであろうことは容易に想像がつきます。
通訳案内士の資格本当に使いますか?
難易度が高いと言われる全国通訳案内士の国家試験ですが、資格を取得しても通訳案内士として稼働する人の割合が低いことも特徴の一つです。
国土交通省が平成25年(2013年)に実施した調査「通訳案内士の就業実態等について」によると、有資格者の約3割しかガイド就業をしていないそうです。
受験者の中には、ガイド就業を必ずしも目的としていない人も含まれ、語学力の証明や転職に活かすために資格取得をしたとの調査結果もあります。
本当は通訳案内士になりたくても不安定な雇用状況ゆえ、諦める人もいるでしょう。
さらに平成30年(2018年)には、改正通訳案内士法が施行され、今や無資格でも外国語による観光案内業務で報酬を得ることが可能となりました
無資格でもトップガイドを目指す気概があるのなら、それも叶えられる時代になるのかもしれませんね。
これから受験される方にとっては、「全国通訳案内士の難易度と格闘することに果たして意味はあるのか?」というのが最大の懸案事項かと思われます。
わたしの答としては
です。
自分に関しては、受験を決意した時からガイド就業する意志があり、「そもそも資格が無ければスタート地点には立てない」といった気持ちでした。
もしもあなたが通訳案内士の合格率に対して、何等かの疑問を感じているのなら、今いちど胸に手をあてて考えてみてください。
その資格、取得後に本当に使いますか?
答がイエスなら、「迷わず受験勉強に邁進」です。